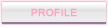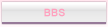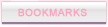|
もじゃりんの日記
Muriel - 閉じた不可逆な世界 ★★★★
骨董というものは数が限られていて、しかもそれぞれに物としての記憶を刻まれている。骨董には怨念が入っているかもしれないから嫌いだ、という人もいるが、人間だって同じこと。それぞれに記憶を刻みこんでおり、その中には怨念だってあるかもしれない。もちろん愛の記憶もあるだろうし、後悔もあるだろう。ただし、それを穿り返してみても先には進まない。とはいえ、蘇らさずにはいられない記憶もある。この映画はそうした記憶にとらわれた人々の閉じた世界を描いている。もちろん彼らの過去は遡って変えることはできないものだ。とうとうRobertを射殺したBernardだって、Murielの殺害という悪夢から逃れることはできない。Alphonseを呼び出したHeleneは、何故そんなことをしたのか自分でも分かっていない。呼び出されたAlphonseは過去の想いからHeleneに迫るが、彼の眼中には連れてきた現在の愛人は入っていない。そんな彼に妻のSimoneのことを思い出させる男が乱入してきて、さらに彼は過去に縛られてゆく。Robertに山羊の雌を連れてきてくれと頼む老人は、その点だけにおいて未来に向けて生きているが、この映画では例外的な人物になっている。そして老人であるだけに、その未来は限られたものである。とりわけ戦争という事実は記憶のなかから消しがたい。個人の意志と無関係に人を殺し、殺され、町は破壊されてしまう。Alain Resnaisの作品には、戦争という典型的な不可逆性をもった記憶が良く描かれる。そこが原点となってしまった人々は悲劇に生きることになる。そんな記憶は無くなくしてしまえればいいのに、なぞと望むことはできない。そもそも人間のアイデンティティは記憶に立脚しているのだから。自分が自分であることは記憶を持って生きることだから。その意味で、単なる反戦争というテーマではなく、人間の存在の原点を描いた作品といえる。映画としてみた場合、Resnaisのズタズタなカットの切り方や混ぜ方は僕の好むやり方ではない。ただ、公開当時の人々に、ある種の新鮮さを感じさせる物だったろうとは思う。いや、現代においても、敢えて言うならそうした残酷な編集のやり方は、それなりの斬新さを感じさせ、映画の主題を明示することを助けている。なおHenzeの音楽は悪くはないが、良くもない。僕が見たのはVHSで字幕は英語。しばしば字幕に訳されていないフランス語があったり、意訳が過ぎるところもあったけど、いかんせん映像がぼけていて、改めてDVDを発注することになってしまった・・。
|
 ブログを作成
ブログを作成
 ブログを作成
ブログを作成